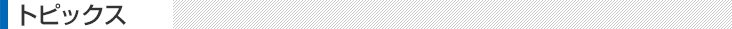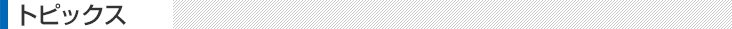企業経営に「デザイン思考」を取り入れる、そのための人材「デザイニスト」の育成を目指すというSTRAMDの教育理念に惹かれて、今年の4月から開講の夜間の社会人コースを受講している。これは桑沢デザイン研究所の内田繁所長が「桑沢を日本で一番進んだデザイン学校に」との強い意図を持って始められた企画で、今デザイン分野が世界的に見て新しい展開を見せ始めた最新の実験コースでもある。

講義の内容は実に幅広く多岐にわたり、戦略デザインと経営に関わる講座を柱に、日本文化のような思考の基本になるものからWebマーケティングやサステイナブルデザインといった「旬」な内容のものまで、バランスよくラインナップされていて、飽きる暇もない。
週に2回、仕事を終えてから3時間の授業。月に1回は土曜日に企業の経営トップなどを招いた特別講義が開かれる。夢中になって受講しているうちに、あっという間に前期が終了した。
前期の講義は「基礎教育と理論」を中心として行われたが、特別講義を含み30講座のどれも大変興味深いものだった。
講義全体の主宰者とも言える中西元男先生の「戦略経営デザイン論」では、銀座松屋や伊藤忠商事など、長年に亘って中西先生が取組んでこられた企業の再生や理念構築から始まる本格的なCIの実例を見ながら企業を蘇らせる「蘇業」の面白さを学んだ。
紺野登先生の「知識経営論」では、Apple、Nokia など「知識デザイン企業」について学び、観察からプロトタイピングに到るデザイン手法、顧客の潜在ニーズをプロダクトとして生み出していく方法論を知ることができた。
各講座で話される先生方の独特の考え方や言い回しに新鮮な驚きを感じることも多い。
内田繁先生が「デザイン概論」で話された、日本文化における「弱さのデザイン」、「全人類が持っている前文化的記憶に訴えかけるデザインは多くの人の心に響く」ということ、半田智久先生が「創造と知性」での中で言われた「日本人はリーダーではなくイニシエーター(改革者)である」などの考え方は、強烈に印象に残っている。
またファッション業界からは横森美奈子さん、WEB業界からは石黒不二代さん、といった各業界の第一線で活躍する方々のお話も、ビジネスのリアリティと迫力のある素晴らしいものだった。



土曜日には、異色の「ワイン&マナー」といった講義も開かれた。実際にワイン事業の会社を起業された松浦尚子さんのワインの試飲を交えながらの講義も、大変興味深く楽しかった。

講義の内容に加えて魅力的なのが受講生の顔ぶれだ。年齢は20代後半から60代まで。職業はデザイナーや建築家からコンサルタント、企業の経営者までと実に多彩で、皆熱心なので刺激を受けるし励みになっている。
5〜6人のグループでひとつの課題を研究して成果をプレゼンテーションするというグループワークは難題だが、個性豊かなメンバーとの交流は愉しく、克服しがいがある。
次々に新しい情報のシャワーを浴び、充分に咀嚼する間もなく次の授業に臨むという毎日を繰り返すうちに、不思議なことに、自分のなかにある種の栄養素が吸収されて蓄積されているような感覚を覚えるようになってきた。

前期で学んだこれらの知識は、すぐに実践に結びつくというよりも、これから後期にかけてより実務に近い内容を学んだときに、吸収されていた栄養素が効いて、実際の仕事に役立つものとなるのだろうと思う。
かつて短大を卒業後、商社に就職していく同級生を横目に、桑沢で学んだことは、私にとって人生最初の大きな転機となった。学んだのはデザインだけではなく、その後の私の人生のあらゆる場面で、桑沢で学んだ「時間」が栄養素となって効いていた。
いまSTRAMDで学んでいることも転機となり、過ごしている素晴らしい「時間」がこれからの私に大きな影響を与えることは間違いなさそうだ。
記: 田辺 千晶(1部56L2Cイ住) プランナー・同窓会理事
●STRAMD ブログURL http://stramd.kds.ac.jp